トルコ:海と鉄道
1890年6月7日、イスタンブルから約11ヶ月の航海を経て横浜港に入港したオスマン帝国海軍エルトゥールル号。航海の目的のひとつには西洋諸国との不平等条約に苦しんでいたオスマン帝国と同様の状況にあった日本との親善を図ることがあったという。のちに和歌山県串本町近海で遭難した同艦から始まる日本とトルコの友好関係は『海難1890』として2015年に映画化された。
1872年10月14日、新橋〜横浜間で日本初の鉄道が正式開業した。エルトゥールル号が横浜港に入港する約8年前の事である。幕末から明治にかけて近代化を推進すべく招聘された御用外国人の存在は有名だが、技術者のみならず鉄道建設に必要な資材も自国生産が難しく英国からの輸入に依存していた。輸入した鉄道資材は開港地である横浜港で荷揚げされており、日本初の鉄道が横浜の地を結ぶこと。言い換えるならば海陸交通の連絡を意識した路線である点は荷揚げ後の資材移動を考慮すれば当然である。
1883年に開業した高崎線は富岡製糸場が位置する両毛地域で生産された生糸を効率的に横浜港から輸出することを目的に建設された経緯を有する。当時、生糸の輸出は近代化政策によって生じる貿易赤字軽減策として重要視されていたことから国家を支える大動脈であったことが伺える。
余談にはなるが、日本とトルコは近代化の過程における類似点が多々指摘されており、高崎線と同様に資源のある内陸から港街へと敷かれた鉄道も多い。日本において鉄道とは「海の向こう」から到来した技術であり、日本の鉄道網も海を介して外国と繋がっているのだと私は思う。トルコの鉄道は何を運び、海を介して何処と繋がり、そして近代史にどのような影響をもたらしたのだろうか。
匿名希望
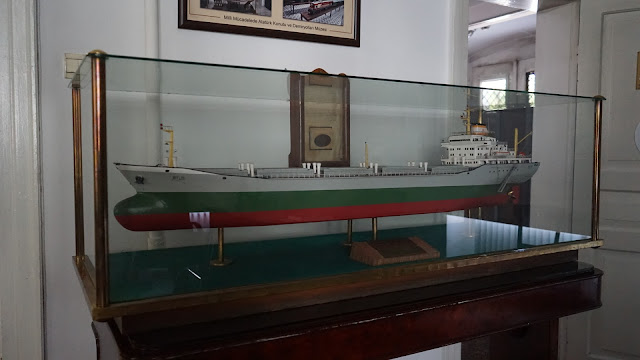







コメント
コメントを投稿